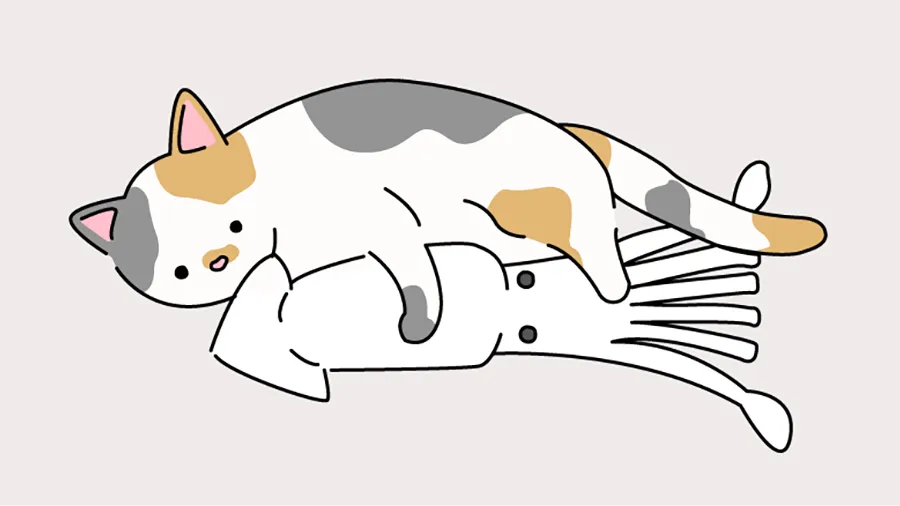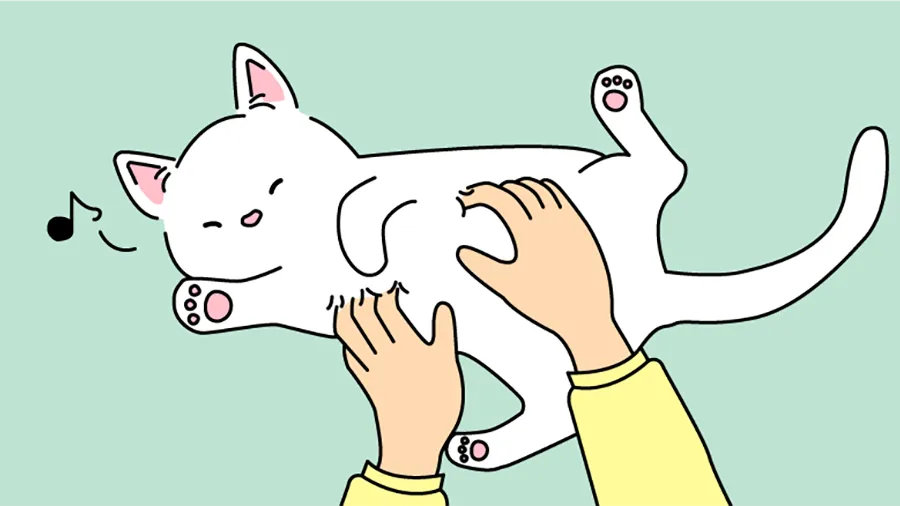
目次

猫がイカを食べると腰が抜ける?
「猫がイカを食べると腰が抜ける」という話を耳にしたことがある人もいると思います。
この話、本当なのでしょうか?
実際に猫がイカを食べると、どのようなことが起こるのでしょうか?
正体はビタミンB1欠乏症
哺乳動物にはビタミンが必要ですが、なかでも猫は犬に比べてビタミン要求量が多いため、ビタミン欠乏が起こりやすいと言われています。
加えて、哺乳動物はチアミン(ビタミンB1)を体内合成できないため、食事からの摂取が必須です。
- チアミン(ビタミンB1):維持期のための最小栄養所要量
- 成犬・・・100kcalあたり 29μg
- 成猫・・・100kcalあたり125μg
通常は、栄養の調整された市販のペットフードを中心に与えている場合には、ビタミンB1を適切に摂取できており、ビタミンB1欠乏症が起こることはほとんどありません。
しかしながら、ビタミンB1を分解する酵素である「チアミナーゼ」を含む食材を大量に摂取した、または長期摂取している場合や、偏食、食事摂取量低下に伴って、ビタミンB1欠乏症の症状が出てくる可能性があります。
つまり、「猫がイカを食べると腰が抜ける」とは、チアミナーゼを含む魚介類(イカなど)を多量または長期にわたり摂取したことによる、ビタミンB1欠乏症の症状であると言えます。
参考:「禁忌食(その4)―魚介類(チアミナーゼ)」ペット栄養学会誌,17(1):44-45,2014(最終アクセス 2022年6月20日)
ビタミンB1欠乏症の症状
ビタミンB1は主に糖の代謝に関与しています。
ビタミンB1が欠乏すると、脳における糖の代謝異常が発生し、主に下肢を中心に運動失調、虚弱、抑うつなど様々な神経症状があらわれます。
症状としては、食欲不振に続いてけいれん性の麻痺がみられます。この麻痺によって後脚が硬直し、特徴的なよろめきつつ歩く状態が起こります。
後脚の麻痺が進行すると立っていられなくなります。
更に進行すると、強いけいれんを起こし昏睡状態におちいり、死亡することもあります。
また、知覚過敏、嘔吐などの症状もみられます。

なにをどれくらい食べたら危険?
生を食べると危険
ビタミンB1を分解する酵素であるチアミナーゼが症状を引き起こすのですが、このチアミナーゼは加熱によってその効力を失います。
しっかりと加熱しているものであれば、猫が食べても直ちには問題ありません。
しかし、チアミナーゼを含む食材を「生」で食べた場合には、ビタミンB1欠乏症が起こる危険性があります。
チアミナーゼはどのような食材に含まれている?
イカはもちろんのこと、その他チアミナーゼを含み、ビタミンB1欠乏症を引き起こす恐れのある食材として、以下の情報があります。
生のイカや貝などの魚介類や、カニ、エビなどの甲殻類はビタミンB1を分解する酵素を持っているため、猫に与えると体内のビタミンB1が欠乏して後脚の麻痺を引き起こします。魚介類は必ず加熱調理をして与えるようにしましょう。
出典元:環境省ホームページ「飼い主のためのペットフード・ガイドライン ~犬・猫の健康を守るために~」(最終アクセス 2022年6月20日)より引用
生の魚介類・甲殻類は、基本的には与えてはいけません。
どれくらい食べると危険?
生のイカを少量食べるだけで、直ちにビタミンB1欠乏症が起こるわけではありません。
一度にたくさん食べた、日常的に食べている、などの状況でないならば、それほど気にする必要はないでしょう。
また、どれくらい食べたら重篤な症状が出るのかなど、個体によって異なりますので、具体的な目安や基準はありません。
生の魚介類や甲殻類は避け、ビタミンB1が不足しないようにバランスの取れた食事を心がけましょう。
もちろん、加熱したイカが入っているペットフードなども、食べさせて問題はありません。
生のイカを食べてしまった時は?
誤って生のイカを食べてしまった時は、それが少量であれば慌てず、まずは食欲不振やふらつきなどの体調変化が無いか、様子をみましょう。
そのうえで心配であれば、念のために動物病院を受診しましょう。
まとめ
猫は、ビタミンB1を分解する酵素であるチアミナーゼを含む食材を生の状態でたくさん食べた場合などは、ビタミンB1欠乏症を起こす危険もあります。
生のイカや貝などの魚介類、カニやエビなどの甲殻類は、チアミナーゼを持っているため、猫に与えないようにしましょう。
もちろん、加熱すればイカを含む魚介類なども猫に与えることはできますが、そこまで積極的に与える必要のある食材ではありません。
加熱されたものが入っている場合を除き、意識して与える必要はないでしょう。

 ご契約者様
ご契約者様
 ご質問
ご質問