犬の歯根膿瘍とは
犬の歯は、根元に向かって細く伸びています。
その根元の部分を歯根(しこん)といい、歯根の部分に膿がたまることを歯根膿瘍(しこんのうよう)といいます。
歯根膿瘍は歯周病が進行して起こります。
歯根の先端は根尖(こんせん)というので、歯根膿瘍は根尖膿瘍、根尖周囲膿瘍とも呼ばれます。
<歯の模式図>
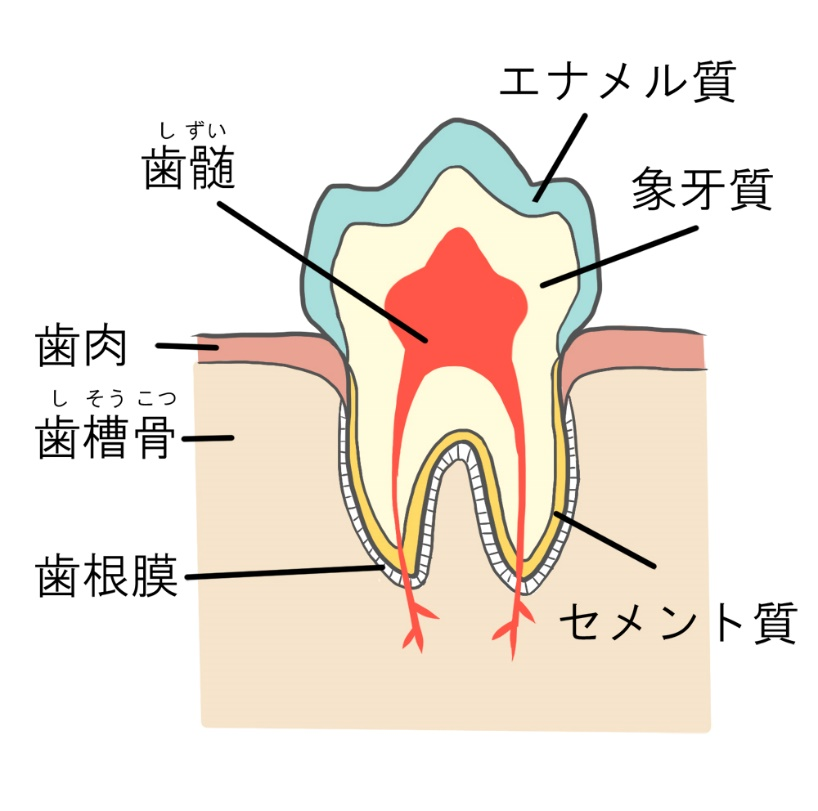
歯根膿瘍は、歯根に膿がたまるだけでなく、骨が吸収され、鼻腔と歯根の間の骨に穴が開いてつながることもよくみられます。
この状態を、口腔鼻腔ろうといいます。
口腔鼻腔ろうは、上顎の歯の根尖が鼻腔と隣り合い、その間の骨が薄くなっている部位の歯で起こりやすいです。
特に上顎の犬歯は根元が深いので口腔鼻腔ろうがよくみられます。
さらに、上顎の犬歯より後ろの3本の歯(第1から第3前臼歯)、また犬歯より後ろの4本目の前側の歯根(第1後臼歯)も、鼻腔との境目が薄くなっています。
犬の歯根膿瘍の症状
歯根膿瘍の症状は以下のようなものがあります。
これらは口腔鼻腔ろうまで進行したときの症状を含みます。
歯根膿瘍の症状
- ご飯を食べにくそうにする
- ドライフードをぽろぽろこぼす
- 食欲が落ちる
- くしゃみをする
- 眼の下がぼこっと膨れる
- めやに
- 鼻汁
- 鼻出血
- くしゃみ
- 歯茎の出血
- 口臭
など
他には、歯肉が下がる、歯石がかなり着いている、歯が揺れ動くなどの状態もみられます。
犬の歯根膿瘍の原因
歯根膿瘍は歯周病が進行したものです。
歯肉炎や歯石、歯根周囲で細菌が増殖して歯根膿瘍の状態まで進みます。
歯根膿瘍の検査は以下のようなものが挙げられます。
歯根膿瘍の検査
- 視診
- 触診
- 口腔内レントゲン検査
- 歯科検査(歯周ポケットの深さの測定など)
- 細菌培養・感受性試験
など
口腔内レントゲンや歯科検査は麻酔をかけて行うので、そのまま治療も行います。
犬の歯根膿瘍の予防方法
歯根膿瘍は歯周病が重度に進行したものです。
歯周病の予防は歯垢を蓄積させないことです。
家庭で毎日ブラッシングをすること、歯根膿瘍に至っていない歯周病をきちんと治療することが、歯根膿瘍の予防方法となります。
気になること、おかしい様子があれば、動物病院で診察を受けましょう。
犬が歯根膿瘍になってしまったら
歯根膿瘍の根本的な治療は、抜歯です。
それと合わせて、抗生剤の投与も行います。
歯根膿瘍は抗生剤の投与だけで一時的に収まることも多いですが、繰り返し再発します。
歯根膿瘍の治療
- 抜歯
- 抗生剤の投与
- 歯石、歯垢の除去(スケーリング、ポリッシング)
など
まだ他の歯が残っていて、スケーリング、ポリッシングなど歯周病の治療を行った場合は、毎日のブラッシングなどのホームケアを行います。
スケーリング、ポリッシング後は毎日のブラッシングを行わないと、短期間で元のように歯石が付くので、注意が必要です。

 ご契約者様
ご契約者様
 ご質問
ご質問


