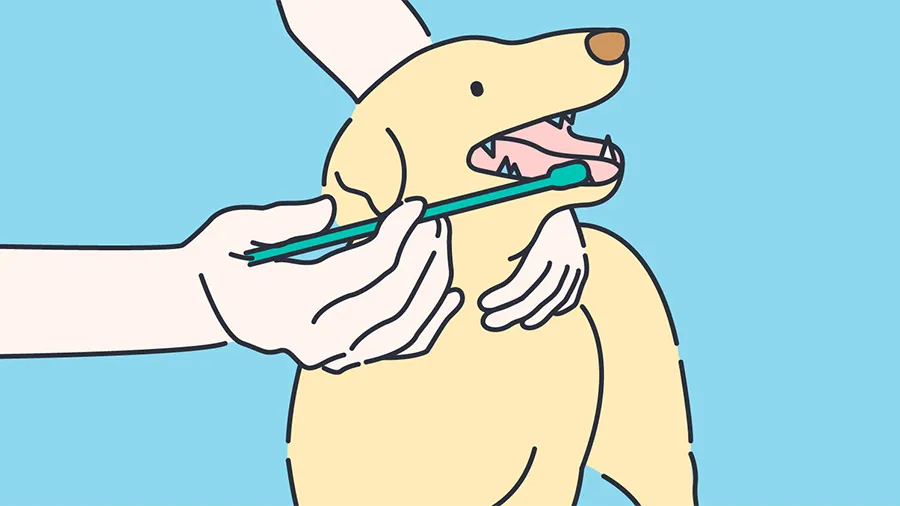犬の歯石とは何?原因は?
ご自宅のわんちゃんの歯は真っ白でしょうか?また、口のにおいはいかがでしょうか?
年齢と共に歯の色はやや黄色っぽくなり、口のにおいも少しずつ気になるようになりますが、基本的には茶色い歯石が付着せず、ひどい口臭もないことが理想です。
犬の歯石とは?
歯石とは歯垢が硬くなったもの(石灰化)です。
歯垢は食べカスと思われる方が多いですが、実は口の中で増殖した細菌の塊です。
歯の表面や歯周ポケットに溜まった歯垢に唾液中に含まれるカルシウムやリンなどが付着して、石灰化したものを歯石と言います。
歯垢の状態であれば歯磨きで除去することも可能ですが、歯石となるとべったりと張り付いてしまうため、専用の器具を使用して除去する必要があります。
歯石の原因
多くの場合は、歯磨きが適切にできていないことが原因になります。
口腔内の環境は犬種や生活習慣、年齢等により大きく異なりますが、どのようなわんちゃんでも、歯磨きが十分でなければ、徐々に歯垢が溜まり、時間の経過とともに歯石へと変化していきます。
適切な歯磨きを行えない理由は様々であり、わんちゃん自身が歯磨きに慣れていないことが原因としては最も多いのですが、歯並びの悪さや乳歯遺残(歯の生え変わり時期を過ぎても乳歯が残っていること)等により、歯磨きを行っていても歯が重なっている部分に歯ブラシが届いていない場合もありますので、注意が必要です。
歯石の確認方法
まずは、口のにおいを確認しましょう。以前に比べてにおいが強いようであれば歯石が付着している可能性があります。
次に、唇を少し持ち上げて、歯の状態を観察します。
多くの場合、歯石は歯の根元(歯茎に近いところ)から付着し始めるため、丁寧に見てあげてください。
奥歯を観察する際には、唇を少し後ろに引っ張ると見やすいと思います。
また、歯の裏側にも歯石は付着しますので、可能であれば大きく口をあけて、奥までしっかりと確認してあげてください。
歯石が溜まると病気になる?
歯石は表面がデコボコしており、細菌が付着・増殖しやすい環境ですので、放置しておくと歯周病のリスクが高まります。
歯周病とは歯肉(歯の周りのピンク色の部分)や歯槽骨(歯の周囲にある骨のこと)等、歯の周囲に起きる病気の総称です。
歯垢の中の細菌が出す毒素によって、歯肉に炎症が起き、赤く腫れ出血しやすくなります。
炎症が続くことで、歯周ポケットという歯と歯肉の間に隙間ができる状態となり、細菌がさらに増殖しやすくなるため、悪循環になります。
また、歯周病が進行すると膿が溜まって、目の下が腫れたり、鼻から膿が出てきたりすることもあります。
重度の歯周病の場合には、軽い刺激であっても顎の骨が折れてしまう恐れがあるので注意が必要です。
犬の歯石の取り方は?
歯石の付着具合により異なりますが、基本的には動物病院で除去します。
軽度の歯石の場合には、外来にて無麻酔で行うこともあります。
中等度~重度の歯石沈着や、歯肉に膿が溜まっていたり、ぐらぐらしているような歯があって抜歯が必要だったりする場合には、全身麻酔下にて処置を行います。
無麻酔歯石除去
ハンドスケーラー(場合によっては超音波スケーラー)を用いて歯石を除去し、スケーリング終了後にはポリッシング(歯の表面を滑らかにするため)を行います。
長時間じっとしていられることや歯石の付着が軽度であることなど、処置を行うにあたり制限があります。
また、状態によっては一度で完了せずに複数回かけて除去を少しずつ行っていく必要があります。
なお、無麻酔での歯石除去は、施術中に誤嚥することで肺炎を引き起こす可能性があるため、十分な注意が必要です。
専門的な技術や知見を要するため、必ず獣医師の処置を受けるようにしてください。
全身麻酔下により歯石除去
一般的には全身麻酔下で歯石を除去します。
全身麻酔をかけた上で、挿管(喉に管を入れること)して人工呼吸器につなぎながら、超音波スケーラーにて歯石除去を行います。
大きな歯石は鉗子により割ることもあります。
歯肉炎が進行して抜歯が必要な場合には、痛みを伴うために、麻酔下で処置を行う必要があります。
術前には必要な検査(血液検査やレントゲン検査等)を実施し、多くの場合は点滴も行うため、年齢や状態によっては1~2日程度入院が必要となります。
全身麻酔下の歯石除去は、犬が動かないので思わぬケガや事故を防止できること、超音波スケーラーによって、表面だけでなく奥歯や歯周ポケットの中まで歯石を除去できること、処置が一度で済ませられること、誤嚥を予防できることが大きなメリットとなります。
自宅で歯石を取る方法
ペットショップ等でハンドスケーラーが販売されていますので、口腔内の状態によってはご自宅にて歯石を取ることも可能です。
しかし、保定する人がいないと処置するのが難しかったり、犬が動いてしまうことで口腔内を傷つけてしまう可能性があったり、場合によっては歯や顎の骨を折ってしまう恐れもあるため、基本的には獣医師にご相談されることをお勧めします。
歯石除去の費用は?
無麻酔による歯石除去はどの程度行うかにより大きく異なりますが、1回あたりおよそ5,000円~15,000円程度です。
全身麻酔下にて行う場合には、術前検査や入院治療の有無、体重等にも大きく左右されますが、概ね30,000円~70,000円程度です。
日常のケア方法は?
まずは、歯磨きをしっかりと行いましょう。
シニア期になると、必ずと言って良いほど歯石は悩みの種となります。
日頃から適切な歯磨きを行うことにより、麻酔のリスクが高まるシニア期における全身麻酔下での歯石除去を避けることができます。
歯磨きを苦手とする場合には、まずお口周りを触って褒めることから始めましょう。
口の周囲を触れるようになったら、次は口の中です。歯ブラシを持たずに歯や歯茎に触れてみてください。
ここまでできれば、ガーゼや指サック歯ブラシを使用することができます。
通常の犬用歯ブラシを使用する場合には、次のステップとして歯ブラシを見せてみましょう。
そして、怖くないものと分かってきたら、歯や歯茎に当てるだけ、少しずつ動かしてみる、歯の外側から内側のケアへと段階を踏んでいきます。
焦らずゆっくり歯ブラシに慣れさせて、お互いにリラックスしながら歯磨きができることを目標としましょう。
まとめ
歯石は、ほぼすべての犬が悩まされるものです。
処置する際、人のように口を開けたままにしておくことができないために、多くの場合は全身麻酔をかける必要があります。
ほとんどのご家族は全身麻酔をかけてまで歯石除去を行いたくないとおっしゃいます。
シニア期になると、必ずと言って良いほど歯石は悩みの種となります。
日々しっかりと歯磨きして歯石の付着を予防することで、望まない全身麻酔を回避することが期待できます。あきらめずに、コツコツと歯磨きを行うようにしましょう。
口の健康は全身の健康に影響します。
たかが歯石と軽視せずに、不安なことや気になることがありましたら、いつでも動物病院へご相談くださいね。
執筆者
石川愛美

日本獣医生命科学大学を卒業後、都内動物病院にて臨床獣医師として勤務。
「予防獣医療」をもっと身近にすることを目指し、2019年に往診を専門とする動物病院「Animal
Care Clinic TOKYO」を開設。
当たり前に存在する「いま、ここに、ある幸せ」を大切にして、健康寿命を延ばすために、食餌選びからセカンドオピニオンまで、飼い主の抱える小さな不安の解消に日々努める。
あくまで動物は「ご自宅で」健康を維持するものであり、その動物のことを一番よく理解し、寄り添うことができるのは、獣医師ではなく、いつも一緒に暮らしている「ご家族」であると唱えており、予防の大切さや日常の中で健康状態を見ることの重要性を発信している。
20年以上、大型犬(フラットコーテッドレトリーバー)とともに生活している。
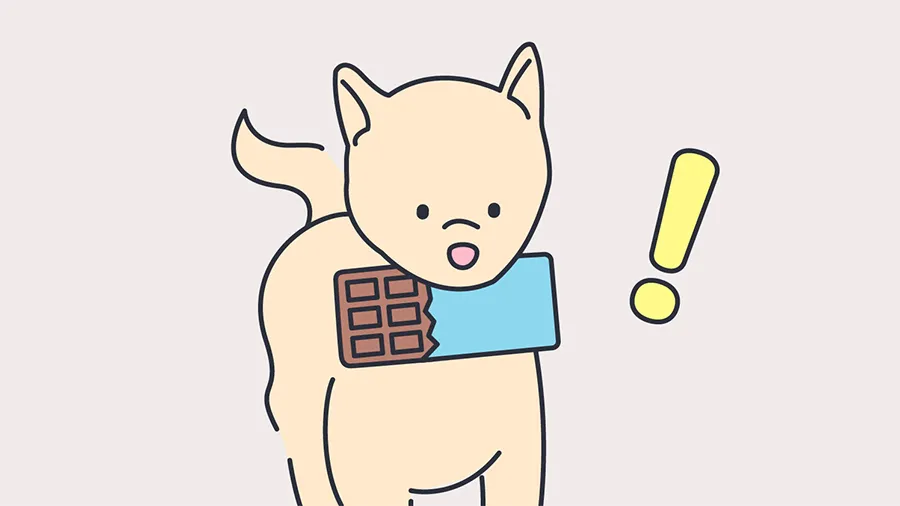

 ご契約者様
ご契約者様
 ご質問
ご質問