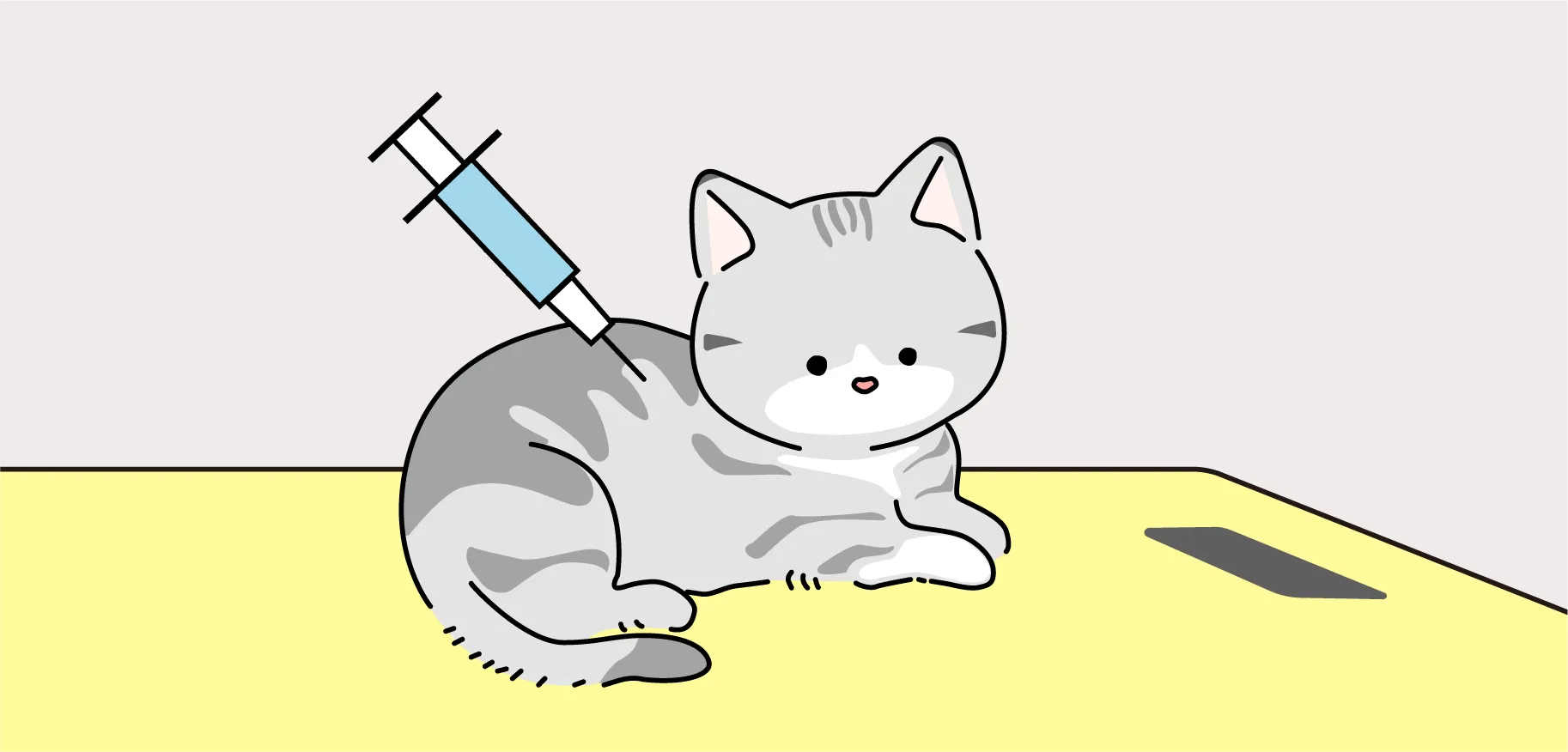みなさんのご家庭の猫は予防接種を受けていますか。
家に迎えるにあたり、何度か耳にする「予防接種」や「ワクチン」という言葉ですが、詳しいことはよく分からないという方も多くいらっしゃるのではないのでしょうか。
猫の健康を維持する上で大変重要な役割を担っている予防接種に関しまして、ワクチンとはどのようなものなのか、どのような働きがあるのかについて、解説していきたいと思います。
予防接種とは?
病気を予防するために、ワクチンを人工的に体内へ入れ、免疫(病気に対する抵抗力)をつけることです。
ワクチンを接種することにより、感染してしまっても発症を予防したり、軽症で抑えたりすることができます。
なお、ワクチンは無毒化あるいは弱毒化された病原体や毒素(抗原)を主成分としており、接種することで感染症にかかることはないのでご安心ください。
猫に予防接種は必要?
基本的には接種するようにしましょう。
感染症の中には直接うつるものだけではなく、空気によってうつるものもあるため注意が必要です。
家の中だけで生活する猫が増えており、外に出ないから病気にもならないという考えから予防接種をしない方もいますが、家族や来訪者から感染する可能性があるため、接種しておくことをお勧めいたします。
予防接種ではどんな病気を予防できる?
猫では混合ワクチンが一般的です。混合ワクチンとは複数の病気に対するワクチンが混ざったワクチンです。
含まれているワクチンの種類により、予防できる病気が違うため、生活している場所やほかの飼育動物の有無、飼育頭数等を踏まえ、動物病院で相談して決めると良いでしょう。
また、狂犬病ワクチンは、犬では1年に1度接種することを法律で義務付けられているのに対し、猫においては義務ではありません。
狂犬病という病気はすべての哺乳類に罹患の可能性があるため、ご心配な場合は獣医師にご相談されると良いと思います。
猫ウイルス性鼻気管炎(猫ヘルペスウイルス感染症)
猫ウイルス性鼻気管炎(猫ヘルペスウイルス感染症)を発症すると、発熱から始まり、くしゃみや鼻水、目やになどが出てきます。
また、細菌感染を合併すると鼻水や目やにが黄色や緑色になります。涙が多くなったり、目の周りが腫れたように見えたりすることもあります。
特に、若齢(6カ月未満)の猫では、脱水や栄養がうまく取れないことで死に至ることもあるため、注意が必要です。
発症した場合には、二次的な細菌感染に対して抗菌薬を使用したり、目やにや鼻汁に対して点眼薬や点鼻薬を使用したりします。
症状により治療は様々ですが、重症化した際には入院となるケースもあります。
以下は治療費例のひとつです。比較的軽度の猫ヘルペスウイルス感染症の例です。
【治療費例】
治療期間:2週間
通院回数:2回
合計治療費用:18,114円
一通院当たりの治療費例:6,500~12,000円
(診察料、X線検査、内用薬、点眼(インターフェロン入り抗生剤))
※2016年1月~2017年12月末の期間に実際にあった請求事例になります。
※こちらに記載してある診療費は、あくまでも例を記載したものになります。実際の診療内容・治療費等は、症状や動物病院によって異なりますので、ご留意ください。
猫カリシウイルス感染症
猫カリシウイルス感染症は、猫ウイルス性鼻気管炎とともに猫のウイルス性上部気道感染症(いわゆる猫カゼ)と呼ばれており、発熱や鼻水、くしゃみなどが現れます。
また、口内炎により食欲不振となることもありますので、若齢の猫では体力が低下し、死亡するケースもあります。
発症した場合には二次的な細菌感染に対して抗菌薬を使用したり、食欲不振がある場合には強制給餌を行ったりします。
また、入院治療となる場合もあるため、注意しましょう。
治療費の一例は以下の通りです。重症化しなかった例で、短期間で良くなっています。
【治療費例】
治療期間:1週間
通院回数:2回
合計治療費用:16,696円
一通院当たりの治療費例:1,000~16,000円
(診察料、血液検査、FIV/ FeLV検査※1、内用薬)
※1 FIV/
FeLV検査:猫免疫不全ウイルス(FIV)、猫白血病ウイルス(FeLV)、それぞれの感染の有無を調べる血液検査
※2016年1月~2017年12月末の期間に実際にあった請求事例になります。
※こちらに記載してある診療費は、あくまでも例を記載したものになります。実際の診療内容・治療費等は、症状や動物病院によって異なりますので、ご留意ください。
猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス感染症、猫伝染性腸炎)
猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス感染症、猫伝染性腸炎)は、嘔吐や下痢による脱水症状を起こし、子猫では特に重篤となり死亡するケースも多い感染症です。
罹患した場合には、点滴や抗菌薬を使用して対症療法を行います。
原因となるパルボウイルスは生存力・感染力ともに強く、家の中だけで生活していても、人の出入りによりウイルスを持ち込んで感染させてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
猫クラミジア感染症
猫クラミジア感染症は、猫同士の接触や空気伝播により感染します。
多くの場合、結膜炎をおこし、涙や目やにが出ます。呼吸器症状としてくしゃみや鼻汁が現れることもあり、重症化すると肺炎を起こすケースもあります。
抗菌薬を使用して、対症療法を行います。
猫白血病ウイルス(FeLV)感染症
猫白血病ウイルス感染症は、感染猫との毛づくろいや同じ食器を使用するなど、接触感染によってうつる病気です。
また、親子感染(妊娠した場合、子猫にも感染する)も起きるために、感染した場合には交配させないことが重要です。
一般的には発熱や貧血などに伴い、食欲や元気がなくなるという症状が見られ、リンパ腫という病気が発生しやすくなります。
発症した場合には、それぞれの症状について対症療法を行います。
猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症(猫エイズ)
猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)は、多くは猫同士のけんかなどによってできた傷口からの直接伝播です。
ウイルスを保有していても症状が出ないこともありますが、発熱や貧血、下痢、口内炎、歯肉炎、リンパ節の腫れや、腫瘍ができることもあります。
発症した場合には、それぞれの原因を取り除くような対症療法を行います。
また、ストレスや免疫力の低下によって症状が現れるため、日頃よりストレスフリーな生活を心がけることも大切です。
予防接種しないとどうなる?
上記のような疾患にかかりやすくなったり、罹患した場合には重症化しやすくなったりします。
特に、子猫では重症化しやすく、死亡するケースもあるため、危険です。
混合ワクチンとは?どの病気の予防接種をすれば良いの?
一般的に猫の予防接種には混合ワクチンといって、複数のワクチンが入っているものを使用します。
予防したい病気の種類により、混合されているワクチンが異なるため、どれを接種したらよいかを獣医師と相談すると良いと思います。
また、ワクチンにはコアワクチンとノンコアワクチンという2種類が存在します。
・コアワクチン:感染すると重篤となるものや広く蔓延しているもの(猫汎白血球減少症や猫ヘルペスウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症など)
・ノンコアワクチン:生活環境や活動範囲によって必要かどうか個々に判断するもの
| ワクチンタイプ |
感染症名 |
3種 |
5種 |
単体 |
| コアワクチン |
猫ウイルス性鼻気管炎 |
○ |
○ |
|
| 猫カリシウイルス感染症 |
○ |
○ |
|
| 猫汎白血球減少症 |
○ |
○ |
|
| ノンコアワクチン |
猫白血球ウイルス感染症 |
|
○ |
|
| 猫クラミジア感染症 |
|
○ |
|
| 猫免責不全ウイルス感染症 |
|
|
○ |
※混合の種類はこのほかにもありますが、多くの場合は3種または5種混合です。
飼育環境に応じた予防接種
生活環境によりお勧めするワクチンの種類は異なります。
例えば、ご自宅の中のみで1匹で生活している猫は3種混合で十分だと思いますし、外で生活することが多い猫の場合にはできるだけ多くのワクチンを接種していたほうが安心だと思います。
また、多頭飼育でFIVあるいはFeLVを保有している猫がいる場合には、部屋を隔離するだけでなく、それに応じたワクチンを接種することをお勧めいたします。
予防接種の費用は?
一般的には3種混合で3,000~5,000円程度、5種混合だと5,000~8,000円程度です。
これに診察料が加算される動物病院もありますので、詳細は動物病院へお問い合わせください。
予防接種はいつごろから始めたら良い?
一般的には8~9週齢のころから始めると良いとされています。
子猫のうちは母子免疫という母親からの抗体に守られます。この母子免疫が存在する間はワクチンを打っても抗体がつくられないため、母子免疫が消失してからワクチンを打つ必要があります。
また、追加接種(2回目のワクチン)はおよそ4週間あけて行うと良いでしょう。
副反応はある?
予防接種を行うことで副反応が出ることがあります。
体質によっても異なりますが、接種後に元気や食欲がなくなったり、接種部位を痒がったり痛がったりすることケースもあります。また、顔や目の周りに腫れやむくみが出てくることもあります(ムーンフェイス)。
ごくまれに、アナフィラキシーショックを起こして死亡するケースやワクチン接種をした部位に腫瘍が発生する場合もあります。
予防接種は少なからず猫に負担を与えるため、体調の良い日に連れて行くようにしてください。また、副反応が出てもすぐに対応できるよう、なるべく午前中に受けるようにしましょう。
治療中の疾病や服薬している薬があったり、過去にアレルギー検査を受けたりしている場合には、それらの情報も伝えるようにしてください。
副反応がある場合
接種後24時間は注意深く様子を観察してあげてください。
元気や食欲は半日程度で回復することが多いですが、普段と違う様子であれば、動物病院へご相談ください。
急激かつ重篤な副反応(アナフィラキシーショック)は接種後30分以内に起きることが多いため、接種後しばらくは動物病院内や病院周辺で待機し、異変があった際にはすぐに処置を受けられるようにしましょう。
また、接種後数日間は安静に過ごし、ストレスを与えないように気を付けてください。運動やシャンプーも控えるようにしましょう。
なお、接種後すぐに免疫ができるわけではないので、数週間は感染に留意した生活を心がけてください。
ワクチンを接種した部位の腫瘍は数年後にできることもありますので、たまに体を触り、腫れている部分がないかどうかを確かめてあげると良いと思います。
まとめ
ワクチンを接種することにより、たとえ感染してしまっても発症を予防したり、軽症で抑えたりすることが期待できるため、基本的には接種することをお勧めしています。
もちろん、ワクチンの効果は100%保証されているわけではありませんが、猫の病気予防策としては非常に効果的であることが実証されています。
予防接種をせずに、深刻な病気に罹患したり、それに伴い身体的・精神的・経済的な負担がかかったりすることのリスクを考えると、ワクチンを接種したほうが良いと思います。
なお、どのタイミングで、どのようなワクチンが必要かは、生活環境や猫の体質によって左右されます。特に、多頭飼育や外での生活が長い場合には、ウイルスチェック(FIVやFeLV)を行い、適切な感染予防やワクチン接種を行いましょう。
ワクチン接種に不安な方は疑問に感じることを動物病院でしっかりご相談いただき、納得した上で予防接種を受けていただけると良いと思います。
疾病予防にはワクチンだけでなく、食生活や運動のバランス、日頃のケアなどが重要です。
これからも猫と健やかで幸せな日々を送るために、「病気を予防する」ということについて、今一度考えていただければ幸いです。
執筆者
石川愛美

日本獣医生命科学大学を卒業後、都内動物病院にて臨床獣医師として勤務。
「予防獣医療」をもっと身近にすることを目指し、2019年に往診を専門とする動物病院「Animal
Care Clinic TOKYO」を開設。
当たり前に存在する「いま、ここに、ある幸せ」を大切にして、健康寿命を延ばすために、食餌選びからセカンドオピニオンまで、飼い主の抱える小さな不安の解消に日々努める。
あくまで動物は「ご自宅で」健康を維持するものであり、その動物のことを一番よく理解し、寄り添うことができるのは、獣医師ではなく、いつも一緒に暮らしている「ご家族」であると唱えており、予防の大切さや日常の中で健康状態を見ることの重要性を発信している。
20年以上、大型犬(フラットコーテッドレトリーバー)とともに生活している。


 ご契約者様
ご契約者様
 ご質問
ご質問